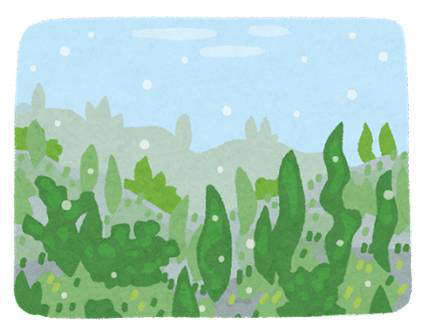ブルーカーボン
中国水工環境コラム第 34 回(2023 年 1 月)
執筆者:中国水工(株)環境アドバイザー 大田啓一
ブルーカーボン(Blue Carbon)という言葉は、2009 年の「国連環境計画(UNEP)」の報告書に登場した新しい言葉です。海の植物に取り込まれた炭素を指します。一方、陸の植物に取り込まれた炭素はグリーンカーボンと呼ばれてきました。ここに言う「炭素」はCO2 の炭素で、光合成によって植物に取り込まれて植物成分になります。大気中のCO2 を増やさないためには、CO2 の発生量を抑える努力とともに、大気中にあるCO2 を大気から除去する努力も必要です。
山林の手入れをして植林すること、あるいは砂地や荒れ地を緑地に変えることなどは、陸上植物によってグリーンカーボンを増やすことになります。その分、大気CO2 は減りますので温暖化対策として重視されてきました。一方、ブルーカーボンについても研究は進んでいて、植物プランクトンの光合成の様子が次第に明らかにされてきました。それによると、植物プランクトンの体は小さいながら、世界の全海洋では陸上植物に匹敵するだけのブルーカーボンを生産しているそうです。
ところが、海の研究には手つかずの場所がありました。それは沿岸の浅い海域です。ここには多様な植物が生育しています。水の中にはワカメやコンブ、ノリなどの海藻とアマモなどの海草が繁茂しています。干潟にも多くの種類の植物が育ち、熱帯にはマングローブ林もあります。このような沿岸生態系の複雑さが研究を遅らせてきました。その状況を変えたのは主に日本の研究者たちでした。彼らは地道な調査と研究によって、浅海域植物のブルーカーボン生産量は植物プランクトンのほぼ半分に相当することを明らかにしました。
干潟、内湾、港湾などは私たちの手が届く沿岸浅海域です。ここの環境を整え、植生の保全・再生を図ることは私たちにできることです。国連環境計画がブルーカーボンを強調した意義はここにあります。国連の報告を受けて、わが国でもいろいろな取り組みが始まっています。横浜市の取り組みにはワカメの地産地消が入っており、福岡市は博多湾の海草アマモの保全を進めています。わが国各地で行われているノリ養殖もブルーカーボンの事業と言えます。
海藻の生産・養殖において大事なことは、成長した海藻を海から陸に揚げることです。海藻を海に放置すれば、やがて分解されてブルーカーボンは元のCO2 に戻ってしまいます。ノリもワカメもコンブも、収穫して利用することが大事です。しかし、収穫期が真冬に来る海藻の収穫は、高齢化する漁師に
は大変つらい作業になっています。
それを軽減するために、海藻を陸上で養殖する動きが始まっています。陸上養殖では一年間に何回も収穫できる可能性があり、ブルーカーボン生産の加速とCO2 削減の向上が期待されます。海藻は海だけではなく、陸でも採る時代が近づきつつあります。