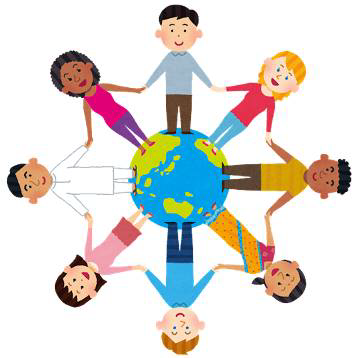人口80億の地球
中国水工環境コラム第 33 回(2022 年 12 月)
執筆者:中国水工(株)環境アドバイザー 大田啓一
国連広報センターは2022 年7 月11 日の「世界人口デー」に、『世界人口推計2022 年版』を発表しました。それによると、2022 年11 月15 日には世界の人口が80 億人に達し、2023 年にはインドの人口が中国の人口を超えるとされています。さらに、2037 年の世界人口は90 億人、2058 年には100 億人に達するとも予測されています。
人口増加は個人消費を活発にし、労働人口も増えるので経済の成長が期待されます。人口減少国にはありがたいことですが、その一方で、食料と水およびエネルギーの確保や住宅の充足などの課題も抱えることになります。その中で特に深刻なのが食料の確保です。国連食糧農業機関(FAO)やユニセフなど5 つの国連機関が共同で発表した報告書『世界の食料安全保障と栄養の現状2022』は、2021 年に8.3 億人もの人が飢餓の影響を受けていたことを明らかにしました。また2020 年には、健康的な食生活を送
ることができない人の数が31 億人に達したとも報告しています。
このような食糧不安と栄養不良の主な原因は、地域紛争、気候変動、貧困や社会的不平等などですが、今年になってそれに拍車をかけたのがロシアによるウクライナ侵攻です。この報告書を著した5 つの機関の代表者も、「この侵攻は穀物、肥料、エネルギー、そして重度の栄養不良の子供たちに必要な栄養治療食の価格を押し上げた」と序文で強調しています。国連事務総長も、国連安全保障理事会において、「武力紛争では、戦闘によって農場や工場が破壊され、人々から穀物を奪い、穀物の不足が生じ、物価が上昇し、飢餓が発生しています」と危機感を露にしました。
このような状況下では、食料不足の国は自国の食料の確保に懸命にならざるを得ません。ご承知のように、わが国の食料自給率はカロリーベースで38%です。残りの62%を輸入しているわけですが、これが国際情勢の変化に晒されています。食料自給率の向上はわが国にとって大変大事な課題で、農水省は2030 年の食料自給率を45%まで引き上げるという目標を設定しています。しかし、それに向けての施策は農家への支援が主なものとなっています。これで本当に大丈夫なのでしょうか。
わが国の食料自給率の向上には、地方社会全体が豊かになることが大前提です。そのためには、農林業の再生と六次産業化、バイオマスの活用、交通網や居住・教育・医療環境の充実を通して雇用と定住人口を増やし、地方で顕著な少子高齢化と人口減少に歯止めをかけねばなりません。政府には本腰を入れて取り組んでほしいものです。
ロシアの侵攻によって荒廃したアフガニスタンで、砂漠に水を引き、農業を再生して60 万人の自活を可能にした中村哲さんが亡くなったのは3 年前の12 月です。先日、福岡で追悼の会が静かに開かれたそうです。